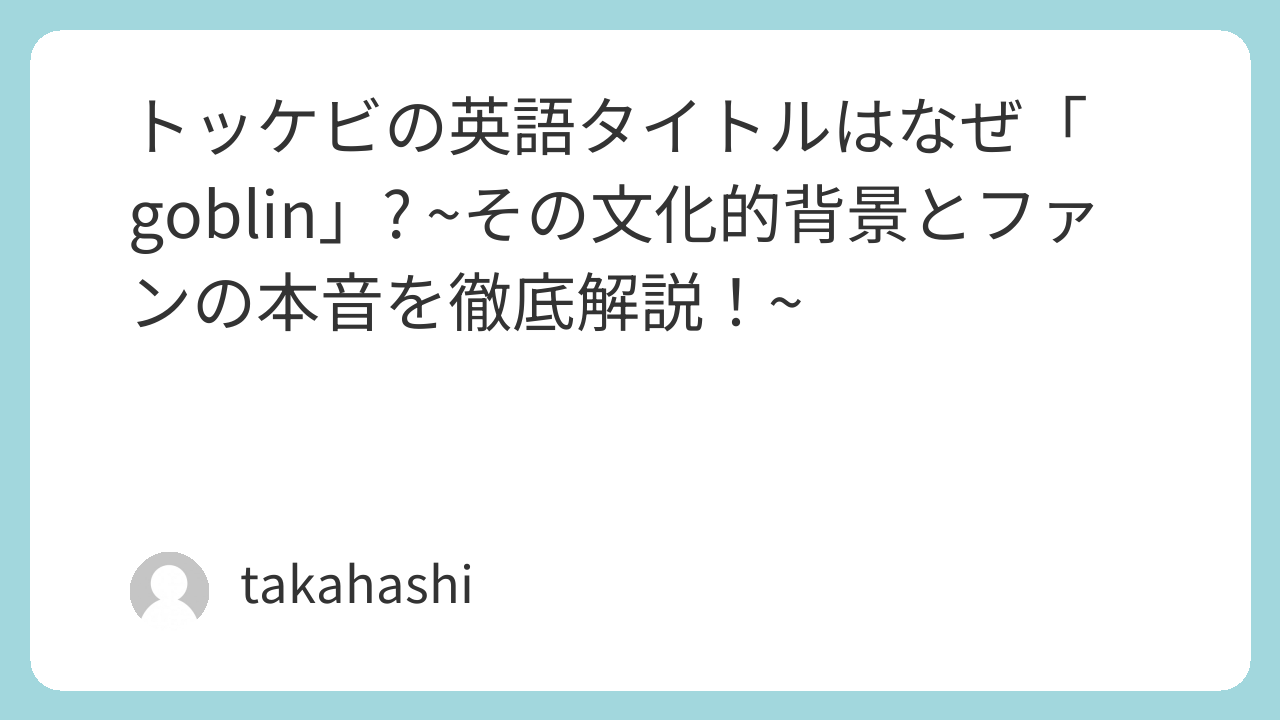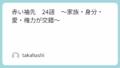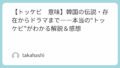韓国ドラマ好きの皆さん、今回は名作『トッケビ』の英語タイトルに込められた意味や、原作韓国の“精霊的な優しさ”と欧米“ゴブリン”の文化的ギャップを徹底解説!なぜ「Goblin」という単語が使われたのか、どんな誤解や共感がファンの間で生まれているのか、公式コメントや口コミも交えて深掘りします。
▼いま話題の続編情報はこちら▼
『トッケビ シーズン2-永遠を旅する心の物語と続編への熱狂-』では、
ファンの期待と作品の深い余韻を詳しく紹介しています。
➡ 『トッケビ シーズン2-永遠を旅する心の物語と続編への熱狂-』を見る

トッケビとは?-作品のあらすじと登場人物
みなさん、Kドラマ好きなら「トッケビ」(英語タイトル:Goblin/Guardian: The Lonely and Great God)はご存知でしょうか?まずは、ざっとあらすじを説明します。
物語は高麗(Goryeo)時代から始まります。主人公のキム・シンは国を救った英雄。ところが、若い王様の嫉妬によって逆賊扱いされ、愛する人々もろとも命を奪われてしまいます。シンは神の裁きを受け「トッケビ」として蘇りますが、これは“永遠の命”という形をした呪いでした。身体には剣が刺さり、その剣を抜けるのは“トッケビの花嫁”だけ。彼は900年もの間、さまよい続けることになるんです。
時は流れて現代。キム・シンは、ピンチの妊婦を助けます。その赤ちゃんこそがヒロインのジ・ウンタク。彼女は不思議な力を持つ女子高生で、幽霊も見えるし、辛い過去を背負いながらも健気で明るいんです。ある雪の日、ついにトッケビとウンタクが出会い、「自分こそがトッケビの花嫁だ!」とウンタクは宣言。トッケビは半信半疑だけど、運命の歯車が動き始めます。
さらに、死神(グリムリーパー)が登場。こちらも記憶を失い、人間らしさに戸惑いながら、不器用な優しさを持ったキャラクターで、彼とトッケビが同居することに!死神×トッケビの“ブロマンス”や、ウンタクとのやりとりが毎回楽しいハプニングや、時に涙を誘う感動シーンに発展していきます。
物語は運命、愛、許し、そして人生の意味を描きます。“不滅の命から解放されたい”と願うトッケビと、“誰にも負けない純真な優しさ”を持つウンタクの、切なくも温かい絆がぐんぐん深まっていくんです。そして死神やチキン店の社長サニーの恋も絡み、登場人物一人ひとりが運命を受け入れ、成長していきます。
悲しみ、嬉しさ、驚き、笑いがギュッと詰まった韓国ドラマの傑作。観ている人の心を動かし、「人生や運命って…」と深く考えさせてくれる特別な作品ですよ!
トッケビの英語タイトルはズバリ!!
まず「トッケビ」を英語に訳すと、「Goblin」が最も一般的です。ですがこの訳、実は作品理解の第一歩で大きなズレが生まれるのです。
- 韓国語で「トッケビ」は民話に登場する妖怪・精霊で、人に幸運を与えたり、イタズラ好きな存在ですが「基本的に善良で人情味がある」キャラクター。
- 英語の「Goblin」は西洋民話では“悪意が強い小鬼、モンスター”や“地下に住む凶悪な魔物”のイメージ。善意や人間味と正反対の認識です。
この単語のギャップ、ドラマ視聴者やファンの間では「ほんとうにGoblinって訳で良かったの?」という議論が絶えません。
英語タイトルの経緯-制作陣の公式コメントとその狙い
なぜ英語タイトルは「Goblin」となったのでしょうか?実は制作陣は「韓国的ファンタジーをいかにグローバルに伝えるか」に悩み、公式でもかなり悩んだ末の決定だったようです。
- 脚本家キム・ウンスクは『トッケビ』企画時点で「Goblin」という単語の持つ西洋的イメージや、韓国オリジナルの“温かみや悲劇性”が伝わり難いことには自覚的だった。
- “Guardian: The Lonely and Great God”という副題が加わったのは、「Goblin=悪い精霊」というイメージを避け、キム・シンが持つ“守護者としての孤独や深み”を込めるため。
- インタビューでは「韓国伝統のファンタジー世界観を海外に伝える工夫」「主人公の悲哀や神話的設定をダイレクトに伝えるため二重タイトルにした」など、文化的ギャップへの配慮もにじんでいます。
トッケビの英語タイトルは微妙?
さて、「Goblin」「Guardian: The Lonely and Great God」は海外ではどう受け止められているのでしょうか?
タイトルへの主な反応
- 欧米・英語圏の多くの新規視聴者は「Goblin」と聞いて暗い・怖い・怪物的な印象を持つ(実際の作品視聴後にイメージが変わるケースが多い)。
- 一部ファンは「Guardian: The Lonely and Great God」の方が、ドラマの重厚なテーマ(愛/孤独/守護)を正確に伝えていると評価。
- 「Dokkaebi」で検索・紹介されることも多く、世界中のファン・記事で使い分けや議論が起こる。
文化・言語の壁 ~トッケビとゴブリンの違い~
韓国民話のトッケビ像
トッケビは朝鮮半島の古代から伝わる存在で、形も性格も地域や時代によってバラバラ。例えば、
- 神霊のように尊ばれたり、
- 鬼火になったり、
- 物が古くなるとトッケビになるという説話も!
特によく知られている特徴は
- “悪戯好き”
- “財をもたらす”
- “悪人には不幸をもたらし、善人には幸福をもたらす”
- 棒や帽子でマジック(金を出す、姿を消す)ができる
- お肉好きだけど血は鬼除け
- 人間と触れ合える距離感と親しみ
こうした性格から、子供の昔話や民話、パンソリなどでも馴染み深く、多くは“笑える、教訓的、憎めないキャラクター”として描かれることが多いです。怖いより「人懐っこさ」や「人助け」など“精霊的優しさ”が根本にあります。
欧米のゴブリンとの違い
一方、欧米の“ゴブリン”は
- “悪意ある小鬼”
- “地下に住み、悪戯・危害・恐怖の対象”
- 童話やファンタジー小説では“モンスター”扱い
というイメージが強く、日本の“鬼”と近い部分もありますが、韓国トッケビほどユーモラスで親しみやすい存在ではありません。そのため、直訳すると「善良な“トッケビ”」のイメージが「悪の精霊“Goblin”」になってしまい、誤解が生まれるんです。
海外評価への影響
- 最初はタイトルによる“ネガティブ先入観”があったものの、一度視聴すると「深い人間ドラマ」や「癒し」が伝わり、SNSなどで口コミが爆発的に広まり高評価に変化。
- 配信サービス・ファンコミュニティでは、タイトルの違和感・ギャップを共有しながらも「それを乗り越えて得た感動」を語り合う空気も生まれている。
実際のファンの口コミ・感想-共感・違和感・誤解
さあ、気になる実際の“生の声”もみてみましょう。SNS・Reddit等でのファンの感想をピックアップします。
タイトルへの賛否
- 「Goblinって何?絶対怖いやつと思ってたのに、泣けるほど優しいドラマだった!」
- 「Guardianの方が孤独や守護を表現してるから好き」
- 「Dokkaebiでそのまま使ってほしかった!」
- 「英語タイトルで検索すると初見に伝わらないけど、作品を観れば納得する」
作品への共感
- 「自分の罪や死への向き合い方、それでも誰かを守りたい気持ち・・・ぶっちゃけ人生観が変わった」
- 「ウンタクの明るさと強さに涙」
- 「死神×トッケビの掛け合いが最高に癒し」
タイトル訳への不満
- 「文化の違いでこんなに違和感があること初めて知った」
- 「“Goblin”じゃない、これはKドラマの“トッケビ”だ!」
- 「Guardian表記だけで世界観を表現してほしい」
- 「タイトルのせいで最初は避けてしまった。もっと伝わる言葉にしてよ・・・」
終わりに
トッケビの英語タイトルを巡る様々な意見や文化的背景は、ドラマを観る楽しみをぐっと広げてくれます。ネガティブな先入観も、作品の世界観に触れることで共感や感動へと変わっていくのが、まさに“トッケビ”の魔法!
\ 視聴者が選ぶ“心に残る名作”再び /
今も熱望される『トッケビ シーズン2』
ファンの声や最新動向をまとめた特集はこちら
➡ トッケビ シーズン2-永遠を旅する心の物語と続編への熱狂-